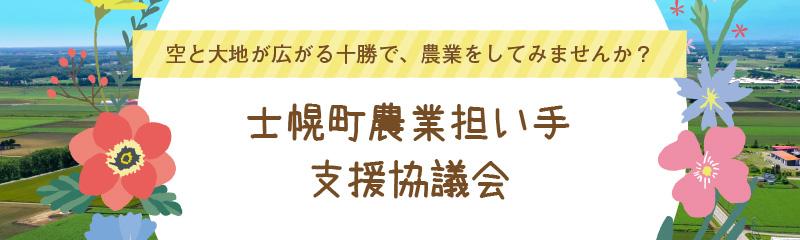大雪山系のすそ野に広がる十勝平野には、じゃがいもや小麦、てん菜、豆類などの畑、デントコーンや牧草などの飼料畑が広がり、日本の食糧生産基地とも呼ばれる肥沃な大地となっています。そんなストレスの少ない恵まれた環境の中で大切に育てられた乳牛から美味しい生乳が搾られています。
町内では約60戸の酪農家で約10,000頭の乳牛を飼養しており、その生乳生産量は年間でおおよそ10万トンにもなります。
JA士幌町の酪農の歴史
士幌町の乳牛飼育は大正10年に導入したのが最初で、本格的には昭和10年代なかばより、冷害凶作を支える手段として畑作複合経営の体制を整える目的で導入したのが始まりです。当時の経営力は弱く、牛乳取引においては乳業会社の独占の中で不利な条件を強いられていました。
そうした状況の中で昭和31年、牛乳集荷販売の一元化と農協による集乳所経営により、士幌農協が全道に先駆けて牛乳共販体制を確立しました。その後40年代に入り乳価安定の基礎を拓いた農民資本による北海道協同乳業(現在のよつば乳業)の設立、高圧電化導入による省力化、育成牧場の充実、畜産リース農場の創立等、畜産総合指導体制の強化が行われました。
その結果、専業化が進むと共に大型タワーサイロ等、多頭数飼育畜舎が整備され、搾乳システムのパイプライン化とバルククーラーの導入によって集送乳体系も合理化、近代化されました。
近年ではより効率的で合理的に管理するため、ミルキングパーラーや搾乳ロボットの導入が進められており、労働力不足の課題に対応しながら省力化と規模拡大が図られています。

集乳検査
士幌町農協では高性能な分析機器を独自に設置しており、酪農家から朝、持ち込まれた生乳サンプルを速やかに解析し、情報をフィードバックする体制を整えています。酪農家は解析データをもとに搾乳の可否や飼養方法、飼料の改善に役立てており、朝持ち込んだサンプルのデータ結果に基づいて夕方の搾乳から対応できるため、生乳を無駄にすることなく搾ることが可能となっています。
乳製品
士幌の生乳は、昭和42年に生産者が自らの手でつくる乳業メーカーとして、十勝管内の上士幌・士幌・音更・鹿追・川西・幕別・豊頃・中札内の各農協が中心となってスタートした北海道協同乳業株式会社(現:よつ葉乳業株式会社)に全量出荷しています。
搾られた生乳は、風味や旨みを逃がさないように搾乳後はすぐに各牧場にあるバルククーラーで冷却され、その後ミルクローリーで出荷され厳正な品質検査を経て工場に受け入れられます。
この恵まれた大地で、のびのびと育った牛たちの搾ったままの生乳を原料に、牛乳・バター・チーズ・ヨーグルトなどが作られています。高い栄養価と群を抜くそのおいしさは、道内はもとより、関東・関西でも高い評価をいただいております。




 JA士幌
JA士幌