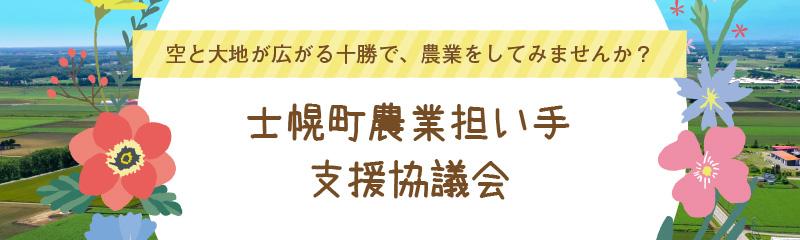視察研修報告 ~廃プラの受け入れ現場と系統肥料について学ぶ~
青年部理事会では、6月13日(金)に青年部員16名で釧路方面へ視察研修を行い有意義な学びとなりましたので青年部による研修報告を一部抜粋して掲載いたします。
(王子マテリア株式会社釧路工場)
当工場ではダンボールの原紙を主に製造しており、私達が出している廃プラや農薬空容器などは、その過程でボイラーの燃料として使われています。現場を見学したところ、廃プラの入ったフレコンバックが大量に積み重なった山があり、5人の作業員が一つ一つ中身を確認して燃やせないものを取り除く作業をしていました。廃プラを破砕機に通す過程で金属異物が混入していると破砕機の刃物損傷がおきる可能性があるため、異物混入が起きないように中身のチェックを徹底していました。実際にフレコンの中を覗くと長靴、ホース、点滴用チューブ、塩ビパイプ、自転車のカゴ等処理できないものが入っていることがあり、ゴミ処理場と勘違いしている人がいるのではないかと思いました。
毎年廃プラ等を出していますが、しっかり分別して出していないことによって現場の方がとても苦労されていることを知り、改めて分別を徹底しなければならないと思いました。廃プラ・農薬空容器は有価物として買い取っていただいているため、処理できないものが混入しないように、農家全体がしっかりと認識する必要があると思います。

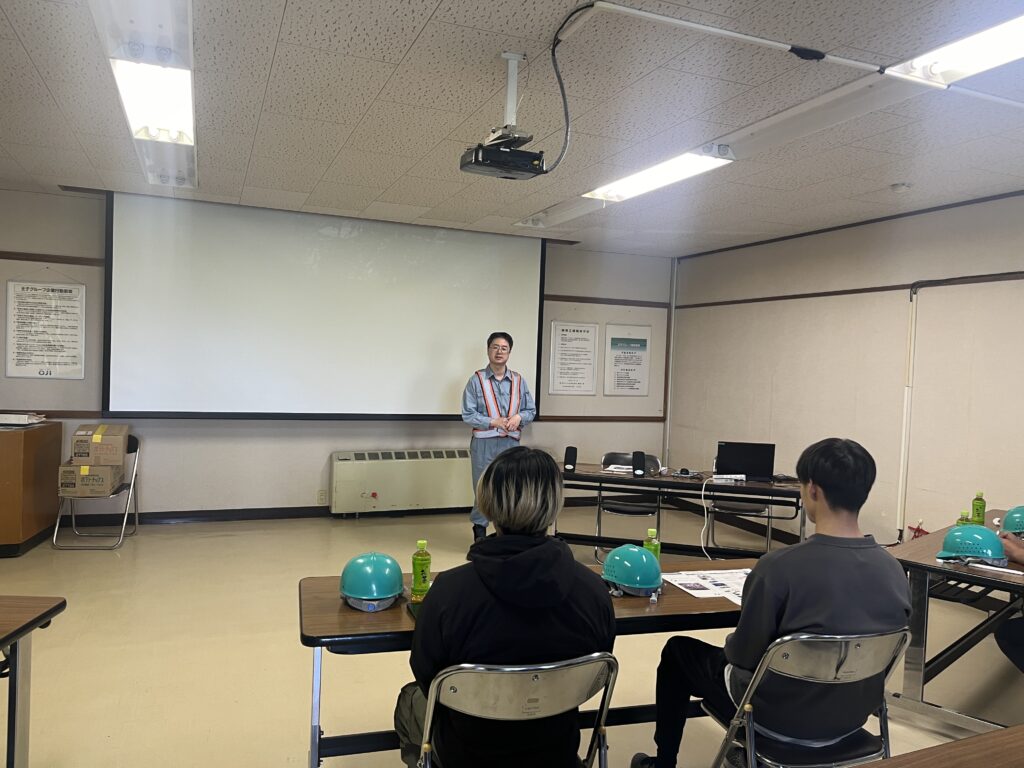
(ホクレン肥料(株)釧路工場)
当工場では世界各地から輸入される原料をもとに化成肥料やBB肥料を加工しており、その製造工程の一部を見学する事ができました。日本は肥料の約9割を輸入に頼っており、日本で生産されているのは硫安などわずかだけとのことでした。
ロシアのウクライナ侵攻に端を発する肥料価格の高騰は、我々農家としては無視できない問題であり、当工場でも昨年度より肥料の価格が5%以上高くなっているとのことでした。このまま高騰が続けば経営を圧迫し、大きな負担になることが予想されるため、土壌診断などを行い、必要以上の肥料を与えないことや、可変施肥の技術を用いて必要な場所に必要なだけの肥料を与える事が求められると思います。その他にも有機肥料や緑肥などを用いる事で地力を向上させ、その結果化学肥料を減らす事ができる可能性もあります。
今回の視察を通じて、農業にとって切っても切れない肥料について改めて考えるきかっけとなりました。



 JA士幌
JA士幌